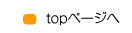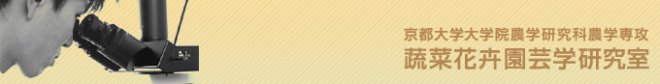
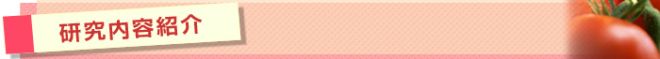
蔬菜花卉園芸学研究室では高品質で安全な野菜と花を安価に周年生産することを目的とし、
基礎研究に基づいて新しい品種やその生産システムを開発しています。
<テーマ:トウガラシ>
関連論文
●Positional differences of intronic transposons in pAMT affect the pungency level in chili pepper through altered splicing efficiency.
Plant J. 100: 693-705. 2019.
●Capsaicinoid biosynthesis in the pericarp of chili pepper fruits is associated with a placental septum-like transcriptome profile and tissue structure.
Plant Cell Rep. 40: 1859-1874. 2021.
●Characterization and bulk segregant analysis of a novel seedless mutant tn-1 of chili pepper (Capsicum annuum).
Sci. Hortic. 276: 109729. 2021.
●Morphological and gene expression characterization of maf-1, a floral chili pepper mutant caused by a nonsense mutation in CaLFY.
Mol. Breed. 42: 32. 2022.
●CaCKI1 causes seedless fruits in chili pepper (Capsicum annuum).
Theor. Appl. Genet. 136:85. 2023.
●An evolutionary view of vanillylamine synthase pAMT, a key enzyme of capsaicinoid biosynthesis pathway in chili pepper.
Plant J. https://doi.org/10.1111/tpj.16573. 2023.
<テーマ:花色>
<ダリアの花のアントシアニンの制御因子と花弁の黒色化機構>
ダリア(Dahlia variabilis)は花色・花型・大きさが非常に多様な花卉です。ダリアの花色は花に蓄積する色素(アントシアニン・ブテイン・フラボン)の有無と量によって決まります。本研究室では、トランスポゾンが転移した変異体を解析することで、ダリアの花のアントシアニンがbHLH転写因子であるDvIVSによって制御されていることを明らかにしました。
またダリアには黒色の花色を示す品種がありますが、これらはなぜ黒色を示すのでしょうか?これまで花弁の黒色化は、アントシアニン色素の高蓄積が原因であるとされてきました。しかし、研究を進めていくうちに、ダリアではシアニジン系アントシアニンの高蓄積が重要であること、そして多くの品種ではそれはフラボン合成酵素(FNS)の転写後遺伝子サイレンシングによって引き起こされていることが明らかになりました。
<黄色色素ブテイン生合成機構の解明と分子育種に向けて>
ダリアの黄色色素のブテインはフラボノイド系色素の中では珍しく鮮黄色を呈する色素で,将来の黄色花の分子育種の標的として有望です.しかし,ブテインを生合成するのはダリアなど一部の植物のみに限定され,その生合成に関わる遺伝子は未解明のままでした.本研究室では世界で初めてAKR13ファミリーに属するDvAKR1がブテインの前駆体であるイソリキリチゲニンの生合成に関与することを明らかにしました.現在はイソリキリチゲニン・ブテインの配糖化に関わる遺伝子や蓄積に重要な遺伝子の特定に取り組んでいます。
<花色・着色の不安定化機構の解明>
同じ個体なのに、違う色の花が咲いているのを見たことがありませんか?こちらの枝では赤色の花が咲いているのに、あちらの枝では白色の花が咲いている。このような現象を示す植物の1つに複色花ダリアがあります(写真)。複色花ダリアでは品種本来の複色花だけでなく単色花を頻繁に生じることがありますが、この原因はエピジェネティックな(=遺伝子配列の変化を伴わない)変異であると考えられます。本研究室ではダリア・トウガラシ・ブーゲンビリアについて花色(着色)の不均一性を司るエピジェネティックな変異メカニズムを明らかにすることを目的に研究を行っています。

関連論文
<ダリアの花のアントシアニンの制御因子と花弁の黒色化機構>
●A bHLH transcription factor, DvIVS, is involved in regulation of anthocyanin synthesis in dahlia (Dahlia variabilis).
J. Exp. Bot. 62: 5105-5116. 2011.
●A basic helix-loop-helix transcription factor DvIVS determines flower color intensity in cyanic dahlia cultivars.
Planta 238: 331-343. 2013.
●Genetic control of anthocyanin synthesis in dahlia (Dahlia variabilis).
‘Bulbous plants: Biotechnology’ CRC Press. pp228-247. 2013.
●Endogenous post-transcriptional gene silencing of flavone synthase resulting in high accumulation of anthocyanins in black dahlia cultivars.
Planta 237: 1325-1335. 2013.
●Tobacco streak virus (strain dahlia) suppresses post-transcriptional gene silencing of flavone synthase II in black dahlia cultivars and causes a drastic flower color change.
Planta 242: 663-675. 2015.
●Quantitative evaluation of contribution to black flower coloring of four major anthocyanins accumulated in dahlia petals.
Hort. J. 85: 340-350. 2016.
<黄色色素ブテイン生合成機構の解明と分子育種に向けて>
●Identification of chalcones and their contribution to yellow coloration in dahlia (Dahlia variabilis) ray florets.
Hort J. 90: 450-459. 2021.
●A novel aldo-keto reductase gene is involved in 6'-deoxychalcone biosynthesis in dahlia (Dahlia variabilis).
Planta 256:47. 2022.
●Identification of two 6'-deoxychalcone 4'-glycosyltransferase genes in dahlia (Dahlia variabilis).
Planta Accepted. 2024.
<花色・着色の不安定化機構の解明>
●Simultaneous post-transcriptional gene silencing of two different chalcone synthase genes resulting in pure white flowers in the octoploid dahlia.
Planta 234: 945-958. 2011.
●Petal color is associated with leaf flavonoid accumulation in a labile bicolor flowering dahlia (Dahlia variabilis) ‘Yuino’.
Hort. J. 85: 177-186. 2016.
●Identification of flavonoids in leaves of a labile bicolor flowering dahlia (Dahlia variabilis) ‘Yuino’.
Hort. J. 87: 140-148. 2018.
●Post-transcriptional silencing of chalcone synthase is involved in phenotypic lability in petals and leaves of bicolor dahlia (Dahlia variabilis) ‘Yuino’.
Planta 247: 413-428. 2018.
●Difference in the CaMYBA genome among anthocyanin pigmented cultivars and non-pigmented cultivars in pepper (Capsicum annuum).
Hort. J. 89: 30-36. 2020.
●Post-transcriptional gene silencing of CYP76AD controls betalain biosynthesis in bracts of bougainvillea.
J. Exp. Bot. 72: 6949-6962. 2021.